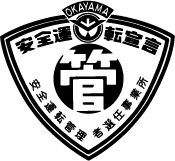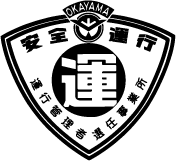安管・運管2025年9月22日更新
「モノが運べない時代」
残業規制4業種に施行
働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が令和6年4月1日、自動車運送業、建設業、医師、鹿児島・沖縄両県の製糖業の4業種に施行されました。
物流は、「生産者」「メーカー」「卸売」「小売」「消費者」「運送事業者」と多様な担い手が関与するプロセスであり、経済活動、また日常生活にとって絶対に欠かすことが出来ない生命線です。
中でも国内貨物運送の大層を占めるトラック運送業は、少子高齢化に伴う生産年齢の人口減少、また、低賃金・長時間労働などの厳しい労働環境を起因とした自動車運転者不足の問題が深刻な上、輸送の小口化・多頻度化により積載効率は低下しており、既に「モノが運べない時代」が来ました。
平成31年「働き方改革関連法」施行では、自動車運送業等は特例として設けられた5年の猶予期間が経過、しかし運行管理者選任事業所における自動車運転者の労働環境は、他の産業と比べて、未だ低賃金・長時間労働、脳・心疾患の労災認定件数ワースト1の状況にあります。こうした背景を踏まえ自動車運転者の労働条件を全産業並に改善し、国内物流機能の持続的な維持を図る観点から、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年 法律第96号)が制定され「標準的な運賃の告示制度」(略称:「告示運賃」)(法附則第1条の3)が設けられました。
「告示運賃」は、自動車運転者の時給を全産業の水準に改善し、法律を遵守し持続的に事業の運営を行う為の適正価格であり、加えて受注者としてとるべき行動・求められる行動として、発注者との価格交渉では、令和6年6月1日施行の新「告示運賃」の公表資料を用いることとされています。
令和6年4月1施行の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(厚生労働大臣告示)」(略称:「新 改善基準告示」)違反となる、自動車運転者に不当な労働を強いる自動車運送事業者は、労基法※1・点呼・運行管理者指定講習・整備管理者の年次未講習・過積・道路法に基づく車両制限違反・名義貸・3ヶ月未点検・社会保険未加入等の法令違反が確認された場合は、新処分基準に基づいて営業停止・事業許可取消・当該「運行管理者」資格の取消等、厳しい行政処分が行われます。
令和7年5月23日強い立場にある親事業者が、弱い立場にある委託先である下請事業者に対して、下請代金の減額、支払遅延、買いたたきといった行為を行わないよう規制する、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)及び下請中小企業振興法(下請振興法)の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)」が公布されました。この改正では、受注者と発注者が対等関係にない語感を解消するため「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払い遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)」、「下請中小企業振興法(下請振興法)」を「受託中小企業振興法」に改称したほか、これまで運送に関しては「運送事業者から運送事業者への再委託のみ」が規制の対象であったところ、新たに「発荷主」から「運送事業者」へ物品の輸送を委託する「物品の運送の委託」も規制対象に加えられ、令和8年1月1日から施行されます。
1990年の規制緩和以降、自動車運送事業は自由競争の状態になり運行管理の基本である「改善基準告示」を無視した労務のもと、格安運賃・過積載などで運送を行う違法行為により運送の質低下を招くことになりました。全産業に比べ(別紙:自動車運送事業のこれまでの経緯 参照)低賃金・長時間労働などが起こり我国の経済活動の基盤となるトラック輸送の存続危機に直面しています。
令和6年4月1日「改正労働法」罰則付き時間外労働上限規制と新『改善基準告示』が施行されましたが、令和6年度(2024年度)の労働基準関連法令違反は未だ81.6%を超え、荷主・物流会社の対策が一向に進まないことに危機感を覚えた政府は物流を持続可能なものにするため、令和7年5月27日に衆議院本会議にて『貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律』、『貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律』(以下「トラック新法」という)が可決され、6月4日に参議院本会議にて歴史的なスピードで可決・成立しました。
令和7年6月11日公布された「トラック新法」は、物流業界の従来の仕組みを大きく見直し、進まない「告示運賃」での値上げ交渉や労働環境改善などの課題に対応する内容となっています。
本改正では、
- ① 真荷主から元請けとして運送を引受ける場合、再委託を2回以内とする努力義務
- ② 何人も無許可営業事業者に運送を委託してはならない。違反した者には罰金、また荷主等に対しても公表を前提とした勧告を行うことができる
- ③ トラック運送事業許可の5年ごとの更新制(貸切バスは、2017年4月1日施行)
- ④ 国土交通大臣が「適正原価」を定めることができること
⇒燃料費、人件費、原価償却費、公租公課、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な経費等で国土交通省が適正な運賃・料金の告示案を作成し、運送事業者はこの適正原価を下回る運賃契約を結ぶことが禁止されます。
⇒物流会社は「告示運賃」を参考に値上げ交渉する場合、荷主から『「告示運賃」は廃止になるだろう』と言われたらどうしよう。といった不安があるが、施行までは現在の「告示運賃」が適用されるので「告示運賃」を参考に交渉するのは当然であり、改正された「トラック新法」が施行されれば「告示運賃」から適正原価に発展的に転化される。 - ⑤ トラック事業者は自らの運行に限らず他の事業者に委託する場合も適正原価を下回らないようにしなければならない
⇒過度な値下げ競争の常態化を阻止し、運賃の適正化により「改善基準告示」を無視した価格競争から重要なインフラである物流が滞る事のないよう、輸送の安全確保をはじめ、品質・サービス重視の競争へ転換が促される。令和8年1月1日施行「中小受託取引適正化法」では、同法の対象となる取引において代金に関する協議に応じないことや協議において必要な説明または情報の提示をしないことによる、一方的な代金の額の決定が禁止されることになる。 - ⑥ この法律は3年以内に施行する
※ ①「下請け制限」、②「白トラ禁止」は交付から1年以内に施行する。
※ 関連法案のうち「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」は、基本理念に基づく国の責務であり公布日に即日施行される。
中小企業庁によると、過去20年の費用上昇分をどれだけ製品やサービスに価格転嫁出来たか示す転嫁率は、27業種の中で「トラック運送」が最下位でした。(「安全運転」2024年8月号中国経済産業局長寄稿資料)
令和6年度貨物自動車運送事業者は6万2千社、その内①保有車両10車両以下の事業者は3万4千社と54.8%、②保有車両30車両以下の事業者は5万3千社と85.4%と全体の8割超えが小規模事業者であり、労働改善に向けた荷主との交渉状況では運送事業者の発言力が低く改善しにくい状態となっており、交渉できない・運べないことにより過積載や運行管理の基本である新「改善基準告示」違反を含む労働基準関係法令違反事業場数は依然80%を越えています。
日本経済を停滞させない為にも、これらの物流問題を解決することは急務であり、安定した輸送の確保、持続可能な物流の実現に向けて皆様のご理解とご協力を深めることが重要と考え、昨年4月号より、関係行政機関の方に寄稿を続けてお願いしています。
労基法※1:労働基準法に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。企業名が公表されることもある為、違反して罰則をうけると採用や事業活動が困難になる恐れがあります。
◆ 2024年4月号は、特集第1弾「岡山運輸支局長 伊藤 雄造様」よりバス・タクシー・トラックの新「改善基準告示」を安全運転管理者事業所の皆様に広く周知する要請をいただき、リーフレットを掲載させていただきました。(B5版)
※誤字訂正:各リーフレット「改善基準告知」⇒「改善基準告示」に訂正いたします。
◆ 2024年6月号は、特集第2弾「厚生労働省局長 森實 久美子様」の寄稿文を掲載いたします。(B5版)
◆ 2024年7月号は、特集第3弾「中国運輸局長 益田 浩様」の寄稿文を掲載いたします。(B5版)
◆ 2024年8月号は、特集第4弾「経済産業省中国経済産業局長 實森 慎一様」の寄稿文を掲載いたします。(B5版)
運行管理者選任事業所である自動車運送事業者の大きな課題である「2024年問題」「2025年問題」に適切に対応し、輸送の安全の確保を第一に取り組んで参りたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。